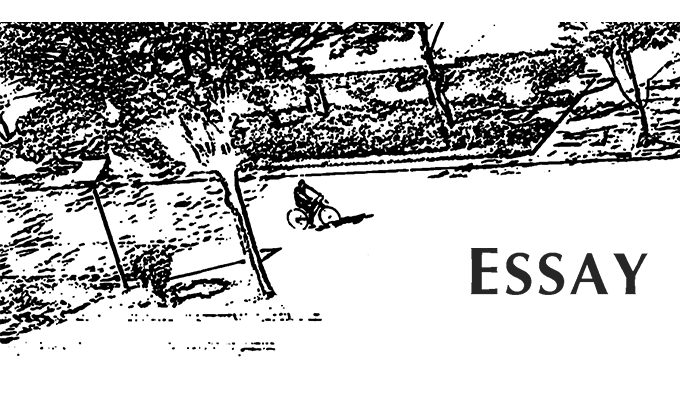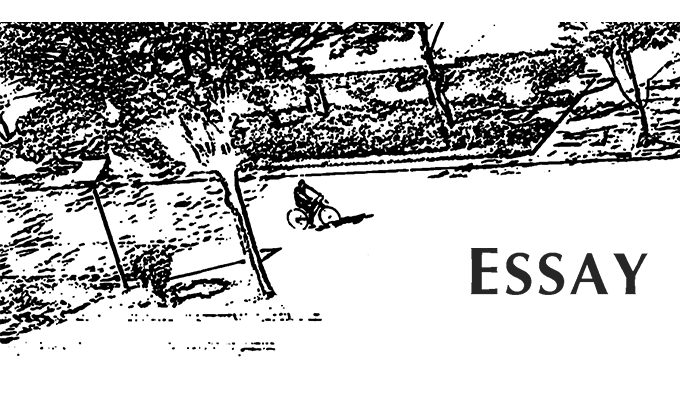Vol.1
そこは誰かにとってのどこかの場所でもある
ビル解体の覆いが外され、少し離れた隣のビルの、裏側に張り巡らされた配管が露わになっている。道玄坂二丁目の交差点で信号待ちをしながら、ここにあったはずの東急本店の在りし日の姿を思い出すのに時間がかかり、しばしそこに立ち尽くした。賑やかなエントランスも、華やかなショーウィンドウも、巨大な屋外広告も、今は跡形もない。一度くらい、写真でも撮っておけば良かったと今になって思った。 信号を渡って、すぐのところにあるスターバックスに入る。試写の開場時間まで、たぶんあと30分はある。アイスコーヒーを少しだけ飲んで、頭をきちんと働かせる。午前中の試写とはいえ10時開始なのだから眠気が襲ってくることはないとは思いつつ、念には念を入れる。レシートの裏面に、何か書き留めておこうと思って、いつも使う0.3mmのシャーペンを出す。カチカチと芯を出す音に誘われて思ったのは、“これからみる映画を、最初に見たのはいつだっただろうか?”だった。
1995年公開の『幻の光』を観たのはいつだっただろう?映画館では観ていないのでビデオで観たはずだった。1995年に17歳の高校生だった私が『幻の光』を知ったきっかけは大学生になってからのことだから、20歳か21歳か、きっとそのあたりで観たのだろうと思う。黒とも言えるような暗部(衣装も含めて)が印象的で、それから2つのカットが映画の中にシンメトリーに置かれている構造が印象的だったことをぼんやりと思い出す。荒れた海と高大な海岸線を捉えた夜のパンショットや、主人公の綺麗な立ち姿も。
『幻の光』のデジタルリマスター版が8月にBunkamuraル・シネマ渋谷宮下で公開されるという情報を目にしたのは、つい先日のことだった。フィルムという世界を突き詰めたような映画だった『幻の光』をデジタルにすることに少し驚きつつも、能登半島での地震を受けて、もう一度映画館にかけるという意味でのデジタルリマスターには深く納得できた。『幻の光』の舞台が輪島だったからだ。8月になったら観に行かねば。そんなことを思っていたところに、試写のお誘いをいただいた。
映画美学校の試写室に入り、だいたいいつも座るような位置の席に座る。もう少し近くで、浴びるように観ようかとも思ったのだけど、いつもと感じ方が変わるような気がしてやめることにした。試写を観る時は、いつもと同じ感覚で映画に入っていけることの方が大事だ。
映画が始まってからのことを、どこからどのように書いていけばいいか、なかなか難しい。最初に書いておいた方が良いような気がするのは、見始めるまでは見直す気持ちでいたのに、見始めたら新作を観ているような感じだったということだ。それもかなりいい新作を。
次に、次に、と繋がれていく1カット1カットが、見惚れるくらいいい画だった。暗部をこれでもかと攻め、しかしそれでいて深い柔らかさがある。耳をすますように、目をすましてみると見えてくる、そんな画もある。こんなに暗部を見つめることができる映画、最近観たっけかなあ?と思う。それでいて、暗闇にふと電気がつき、電球の光というものを再認識したりする。能登に移ってからの画は圧巻だった。例えば、姉と弟になったふたりの子どもが輪島の風景の中を遊びながら歩き回り、駆けていく。水田を駆けるふたりが水面に映る。そのきらきらとした美しさ。例えば、林の中を歩く葬列に舞い降りる雪。雪は、舞い降りるものもあれば、海からの風に煽られ舞い上がるものもある。複雑な風に揺られる雪が幻想的で、思わず、うわっ…と言葉が漏れ、しばし言葉を失いながら、見惚れた。
画だけではない。鈴の音。波の音。ミシンの音。ラジオの声。テレビの声。鳥の声。ガタガタする窓の音。風の音。それらをどんなトーンでどんなテンポにするか。1つ1つ丁寧に紡がれていく。1つ1つ丁寧なのは、編集にもいえる。1つのカットに少し集中できるだけの時間を編集が与えてくれる。それでいて、切ることで繋がれていく感じ、的確なテンポを作っていく。そして音楽。20数年前の記憶には、音楽がなかった。なぜだろう。こんなに綺麗な弦楽器の音色が流れていたのに、不思議なものだった。最後に、弦楽器はそっと違う楽器に変わる。映画を作ったことのある人であるなら、考えればそうするかなと思う変化だけれど、迂闊にも涙が出た。衣装も、画も、人も、人の中の心も、最後にそっと変化を見せる。数ミリメートルのような変化が見る人の心を大きく動かす。それに驚いているうちに、映画が終わった。先ほど、迂闊にも涙が出た、と書いたが、映画を観ていて何度か涙が出た。20数年経って、映画の中に、重ね合わせられる、重ね合わさる何かが増えたのだろうと思う。昔はただ見過ごしていたであろうシーンに、今は涙が出た。
試写会場の明かりがつき、立ち上がる時間が来た。どこかで寄り道でもして余韻に浸っていたい気分を追い出しながら、駅に向かうまでにあとどれだけの猶予があるかを腕時計で確かめる。あんまりない…。地上階までの階段を登り、外に出る。気分はまだ引きずったままだ。いい映画を観た後はしかたがない。
道玄坂二丁目の交差点で信号を待つ間、ふと、映画の中にあった輪島の朝市を思い出した。市場のT字路を見ただけで、そこがどこだか分かり、今はたぶん、涙する人々がいる。そう思うと、映画というものが少し途方もないものに感じた。映画の中には、撮影の意図とは別にしてたくさんの風景が写っているものだ。輪島の朝市も、あるいは、能登ではない前半部の1つの街角も、そこは誰かにとってのどこかの場所でもある。映画は完成すれば作り手から離れていき、やがて観客に届き、そしてある時はふと、誰かのための映画になったりもするのだ。そのことに、改めて気づかされた。
いやはや、しかし、大した午前中だった。うっかり大変なものを見てしまったものだ。でも試写であることにちょっとだけ感謝した。8月になれば、またこの映画を観れる機会がやってくる。もう一度観ようと思った。その時は、もう少しスクリーンに近い席で、浴びるように観たい。うん。浴びるように観よう。
|
|