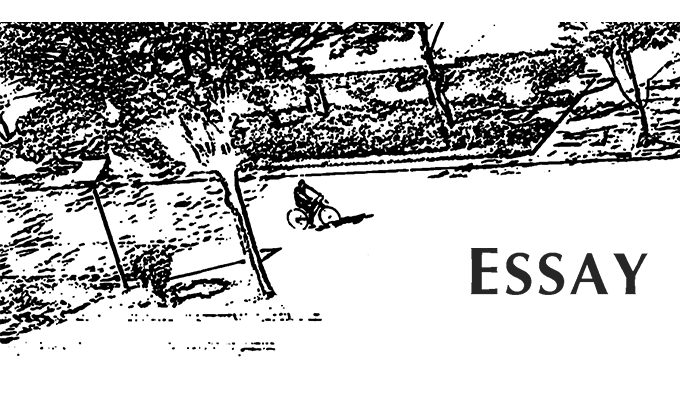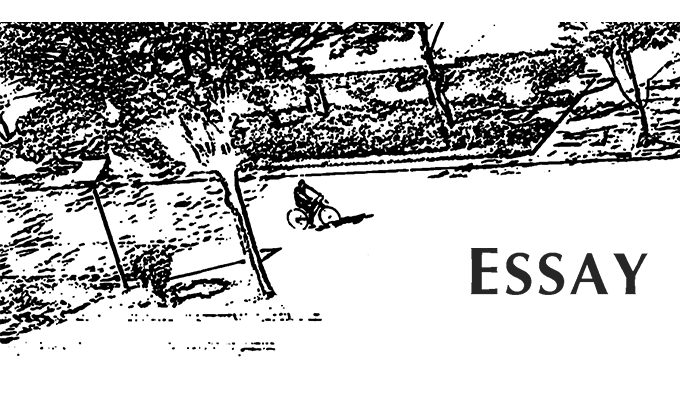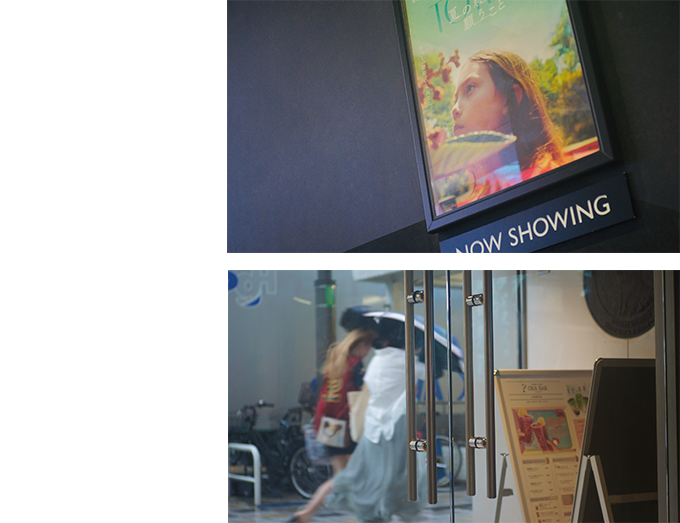Vol.3
よく言葉にできないまま、できないままで
昔、江國香織さんの小説を読んで、その脈絡がないようにみえて実は解体できないほど密接な各エピソード関係性に、大きな驚きを覚えたことがある。ひとつひとつのエピソードが、その時には意味がよく分からないが、読み進めていくうちに、後になって、ふと何のことだったのか(あるいは何のためのものだったのか)が分かったりする。後になって分かるものの、それまでの間が思う以上に長かったり、謎が解けたりする訳ではないので、伏線とは少し感じが違う。けれども、すべてはどれかが無くなっては成り立たない。江國香織さんの小説には、そんなところがある。今見終わった映画を思い返しながら、そんなことを思い出した。
この映画を見ようと思ったきっかけは、主人公である女の子の年齢が7歳だったからだ。7歳の頃というのは、大人になるまでの間の中では、世界が大きく変わる年齢のひとつだと思う。何より小学校に通い始めることで、自分を取り巻く環境が変化する。それから、言葉を、話し始めるではなく学び始める意味で、スタート地点に立つのもこの頃だと思う。そして、何かの死や、誰かの死というものに、触れ始める頃でもある。そういった年齢を、どのように見つめるのか、興味が湧いた。
映画を見ると、そこにはまずたくさんの「生」があって、ひとつの「死」(もうあとわずかで死に至る)があった。そのひとつの「死」を女の子がゆっくりと感じ取っていく様子を、急がず、語ろうとせず、映していく。映画というものは、もともと言葉にできないものを映し出すものだと思っているのだけれど、これはまさしくそんな映画だった。そのうえ、映画を見たのだが、このような映画はいまだかつて見たことがないように思えた。語ろうとはしない、そういう映画だと思う。語ろうとしていたものは、見ているうちに分かってくる。すべて、見ているうちに分かってくるのだ。でも、語ろうとしないところから入る、それが成り立つことを、初めて目にしたようにも思う。
映画の中のひとつひとつの細かなシーンは、いつもその途中のどこかに宝石のような瞬間が潜んでいて、いったいどのように脚本が書かれていたのか、たとえばシーンの始まりはどのように書かれていて、終わりはどのように書かれていたのだろう、というようなことを実際に見てみたい衝動に駆られる。想像するに、実際に脚本に書かれた始まり方よりも少し前(つまりは書かれているところよりも少し前の時間)から撮り始めて、終わりも同じように終わりの部分でカットをかけない、そんな感じのことをしたのではないだろうか、と思う。また、脚本にはもしかしたら、誰かの視点からのナレーションが書かれていたかもしれないし、あるいは襯染という技法が使われていたかもしれない、とも思った。そしてそれらを最終的に外してみたら、もしかしたらこのような映画になるのかもしれない、とも。いずれにしても、いわゆる脚本の構成とは遠く離れた映画がここにはあった。
それは撮影方法にも当てはまる。いわゆる映画の撮影とは、少し違う。冒頭のシーンで主人公の女の子がうっかりカメラ目線になることからも、一瞬ドキュメンタリーかと思ってしまったり。また、手持ちカメラで、1シーンはほとんどカットを割られない。そのようなことから、あたかも、誰かの視点がそこにあるかのように感じたりもする。4:3のスクリーンサイズも、そのような気にさせる。では誰だろうか。映画を見ながら、私はその視点の確かさに、どこか安心する感覚を覚えた。誰かを執拗に見つめるでもなく、カメラを振り回すような不安定さもなく、確かな目線と距離感を持った、視点。フレームの外に広がる世界を、きちんと聞き取っている耳を持った視点。おそらく、監督自身の目線だと思う。この映画には、思い返してみるに、カットバックがひとつも無かったように思う。そのことからも、物語を語るための技巧としての撮影があったのではなく、つまりは物語が映し出されているのではなく、監督が思い出しているものを、監督の目を通して私たちが見ている、これはそのような映画なのだろうと思う。この映画のインパクトは、物語の起伏上にあるのではなく、シーンの途中の宝石のような瞬間にこそある。
最もインパクトのある瞬間は、ラストカットにある。主人公である7歳の女の子は、みんなで集まったこの日のお祭りのような夜の意味を、よく言葉にできないまま、できないままでしかし理解する。その、7歳の頃の、独特な感じ。この子がそれを言葉に置き換える時はいずれやってくるが、今はまだその時ではない。その感じをそのまま映画の中に焼き付けたラストカットは、言葉というもので表せない映画という独特な世界がそのまま焼きついた、稀に見るワンカットだった。
映画館を出ると、外は激しい雨だった。紀伊國屋書店に向かおうと思っていた足をしばし止め、入口の映画のポスターの前で、雨がおさまるまでの少しの間、映画の余韻にしばし浸った。
|
|