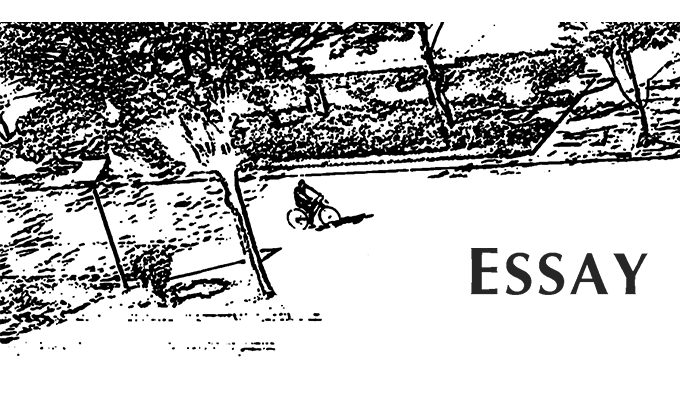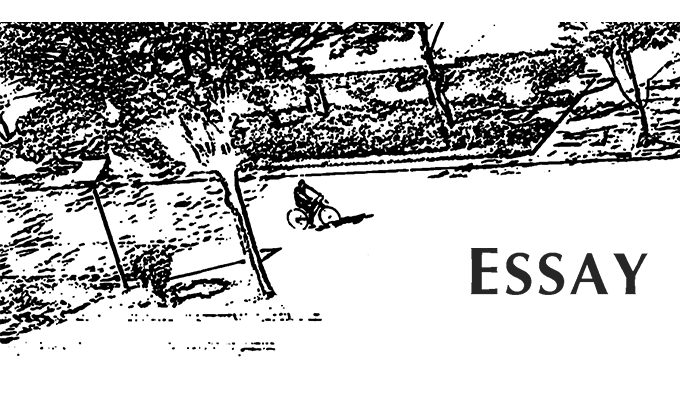Vol.6
冷たいけれども確かな陽光が
図書館の書棚を眺めていたら、昔よく読んだけれど今はもう手元にない映画本を見つけた。紫色の表紙が懐かしく、手に取ってページをめくってみたら、思いがけずエドワード・ホッパーの絵に関するエッセイが出てきた。思わず、あっと声が出る。その昔、何度も読んだエッセイだった。そこにはヴィム・ヴェンダース監督やデイヴィッド・リンチ監督の映画ではよくホッパーの絵が引用されると書かれていて、私はこのエッセイでエドワード・ホッパーという画家を知り、ホッパーの絵を追いかけているうちに好きになってしまい、多数収蔵しているホイットニー美術館にも行って見た。
何度も読んだエッセイだったのに、この本に載っていることをすっかり忘れてしまっていた。まあ読んでいた頃から四半世紀も経っているし、と自分に言い訳がましく言い聞かせ、しかしここで再会したのも何かの縁かと思い直して、借りて帰ることにした。2025年がもうあと数日でやってくる、年末のある日のことだった。
2024年には、もう一つ、ホッパーの絵との再会があった。秋の東京国際映画祭で観た『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』。ペドロ・アルモドバル監督の最新作で、思いがけず出くわした。映画の中では、まずホッパーの絵そのものが登場し、その後、引用される。ホッパーの中のこの絵を使うのかと、まず驚いた。というのも、今回用いられたのはホッパーの中でも日中の絵で屋外のもの、トーン使いも明るい方の絵だからだ(とは言っても、ホッパーなのでどこか冷たく静かで孤独感漂う絵ではあるのだけれど)。ホッパーの絵というと、夜と光のバランスや室内の照明のトーンやコントラストの参考として用いられることが今まで多かった。それに対して今回の映画では、どこか今までとは違う引用の仕方であるように見えてならなかった。なんだろうか。おそらくは孤独か。いやもう少し先の、なんとか言葉にしてみれば、「人は一人一人だ」だろうか。この映画に出てくるホッパーの絵には、五人の人物が椅子に座っているが、一人を除いて皆同じ方向を見ていて、しかし五人の中に会話のような空気はない。一人一人が、同じ何かを見ているようであり、皆、自然の中に居ながら、別の世界にいるように馴染んでいない。そのような絵だ。と書くと、暗い絵のように思えるかもしれないが、ホッパーの絵には、どこかに必ず、冷たいけれども確かな陽光が、もしくは光で照らされた部分があり、静かではあっても暗くはない。一人一人、であることを、そのまま尊重している、ようにも思える。
安楽死がテーマの今回の映画が、死をテーマにしていながら暗い印象を持っていないのは、どこかにいつも、ホッパーの絵のような冷たいけれど確かな陽光が、感じられるからだと思う。そのどこか明るいトーンの印象は、登場人物の着ている服の色にも表れる。黄緑と赤がよく使われ、二つの色は常に画面の中にあると言っても過言ではない。二つは混ざることはなく、存在する。一方の死までの旅を共にするふたり旅。一方が黄緑を着ていれば、もう一方は赤。それがひっくり返ることもある。またひっくり返る、そんなことが繰り返される。それは、おそらく、一方の色からもう一方の色への変化ではなく、二つの色が常に共にある、ということなのだろうと思う。二つの色が同時に届く、ということによって、それ自体が一つのテーマとして伝わってもくる。この映画は、そんな風な映画に見えた。その一つのテーマはなんだろうか。答えが出かかった時、ふたり旅がスクリーンの中で終わった。
|
|