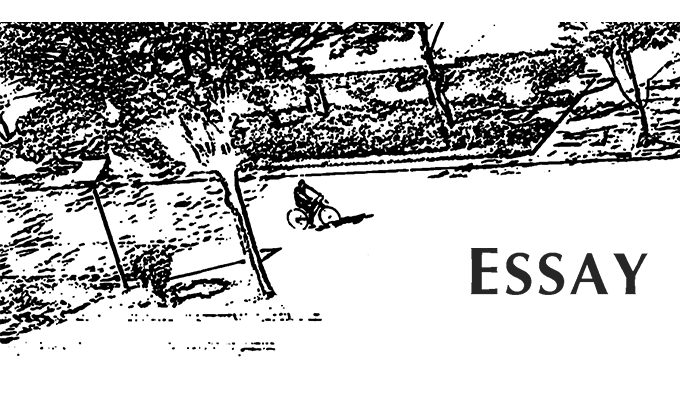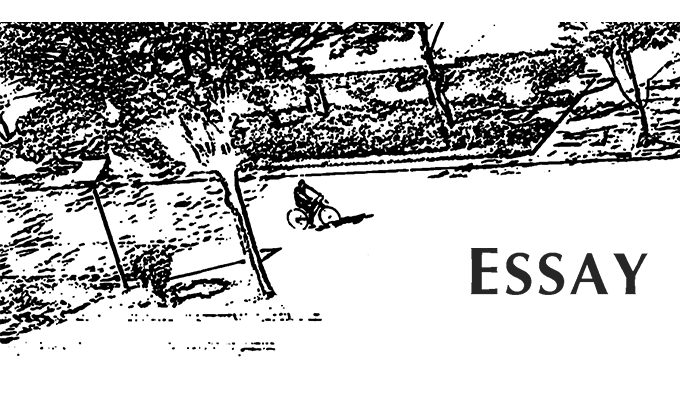Vol.8
現実に起こるかは分からない、けれど
この春は体調が乱気流に巻き込まれたかのような状態で、なかなか映画館に足を運べなかった。ここ数日も喉が腫れて声が出なくなったりした上に軽い寝違いまで起こしてぐったり。うーんと俯いていた。しかしそれでも、観たい映画があると少し変わるもの、のようだ。公開している間に一回は観に行かねば、と思った映画があって、「えいっ」と身体に声をかけて映画館に行ってみた。それが映画『教皇選挙』。次の教皇を決める投票“コンクラーベ”を舞台にしたミステリー映画だ。何にそんなに惹かれているのか、実は自分でもよく分からなかったのだけれど、よく分からないが惹かれている時は、観に行った方が良い。という訳で新宿に出かけ、寝違えた首と背中にあまり負担がかからない後方席を選んで座り込んだ。
映画が始まってものの5分でその音のキレ味に驚いた。緻密に作り込まれた撮影トーンや一級の演技も唸るばかりだったけれど、非常に強い個性で観客を映画に引き込ませているのは音であり音響だったと思う。とても複雑な旋律の音楽がこの映画を引っ張っていく。それはコンクラーベという行事の難しさや複雑さそのもののように聞こえる。弦楽器のうねりがあったかと思えば、何かのパーカッションが引っ掛かり合うように音を重ね刻む。そういった音楽に翻弄されながらその間に、衣擦れの音、呼吸、扉の音が聞こえ、その音響のキレ味の鋭さといったら、漫画のページに大きく太く表現される擬音語のような感じでもある。逆にここまで攻めても面白いものなのだなと聞き惚れてしまった。扉が閉まる盛大な音だけでも、広い映画館に来て良かったと思った。
そして、そのような盛大な擬音語と複雑な音楽が渦巻く息苦しい密室状態の礼拝堂に、ふと、自然音が聞こえるシーンが、最後の方に出てくる。その自然音はなんともさりげない音で、その時ふと、そういえば神というものが作ったものは1つではなかったということを思い出すことになる。このシーンを観ると、この映画における〈脚本〉というものがストーリー設計だけでなく空間設計、音の設計をも網羅していることを実感せずにはいられない。映画脚本というものの奥深さを改めて感じ取ることができて、それは大きな経験だった。
大きな経験だったといえば、もう一つ。ミステリーと、この映画のラストについて。ミステリーというのは、“あらかじめ語られないこと”というのがどこかにあるもので、それをどこにし(何にし)、どのように明かしてゆくかが見せどころになる。その明かし方については、小説に“小説にしかできない手法”があるように、映画にも“映画にしかできない手法”がある。この『教皇選挙』の手法は、それに該当するものだった。映画にしかできない、そう思う。原作があるので文章でもやはり可能なのだろうけれど、映画で観る方が驚きは遥かに大きいと思う。観ている側が、「観ていたはずなのに」と思うからである。観ている側が感じる“してやられた感”は、今回は文章よりも映画の方が断然勝ると思う。過去に『真実の行方』や『ユージュアル・サスペクツ』といった映画にあった“してやられた感”に今回の映画も少し近い。しかしこの映画での“してやられた感”の後に来る重みと一種の爽快さは、格別とも思う。そのような映画の仕組みと、台詞に出てくる“確信”を組み合わせて作品を作る構想には、もうただただ唸るような感嘆の声しか出なく、また格別なのは、そのラストが、現実に起こるかは分からないが、現実に希望を見出すラストであったからだ。
現実に希望を見出すラスト、というものをここ数年、探していたように思う。そういったものは今後あり得るのだろうか、とも思っていた。今現在、予想もできない悲惨な現実の世界を日々目の当たりにしながら、どのような描き方があるのだろうかと、思っていた。しかし今回、『教皇選挙』を見て、ああ、在る、と思うことができた。現実に起こるかは分からない、けれどそのようなラストを描く道は映画にあるのだと、この映画は示してくれたように思う。それは現実に希望を見出すラストであったと同時に、映画に希望を見出すラストでもあった。
重い身体を引っ張って観にきてよかったと思った。大きな経験ばかりだった。そしてエンドロールを見ている間、ふと、思ったことがあった。この映画を観ている間私はいろいろなことをすっかり忘れていられた、ということだ。それは、些細なことなのだけど、そういえばそれは、映画というものの存在意義の一つではなかったかと、思い出させてくれた。観ている間はなんだかすべてを忘れさせてくれる。かつては映画を観るとそのような気持ちを味わうことも多かったのに、それが今ではめっきり無くなってしまっていた。けれど、映画にはまだ可能性があるのだろう。そう思ことができた。
|
|